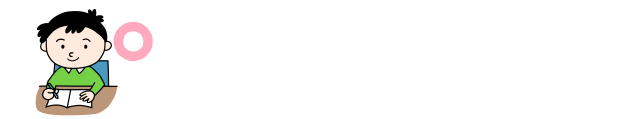生後半年でつかまり立ちは早い?
仕事ではないのですが、知り合いの方から乳児の発達について相談を受けました。
内容は「生後半年の自分の子どもがつかまり立ちをするようになったが、早すぎるのではないか?と心配している。
周りからも股関節や膝関節に良くないのでさせないほうがよいと言われるのだがどうなんでしょう?」というものでした。
よく「はいはいをあまりせずに歩くようになったが、問題ない?」などの体の成長や発達に関する親御さんの心配の声を時々聞きますので、このブログでも子どもの運動発達の視点から書いておきたいと思います。
なお、ここで書いていることは、あくまでも一般論です。
子どもの発達は様々なので、このエントリーを読まれてもなおご心配なら専門家の判断を仰いでください(私も専門家の端くれですが、直接子どもさんを拝見しているわけではないので具体的なことが書けませんのでその旨ご理解をいただければと)。
さて、生後半年でつかまり立ちをしたことについてまず結論から書きます。
「心配ないです」。
もう一言書くと、「子どもさんが自分で勝手のしていることなら、ほっといてOKです」。
親御さんよりも祖父母の方々に「やめさせたほうが良い」と言われる方が多いように思います。
そう思う理由としては、「早い時期から体重をかけると関節の発達(形成)に支障がある」とか、「O脚になるから」ということがあるようです。
これは単に「そう思い込んでいるだけ」なのですが、このお話をする前に、子どもの発達について簡単に説明します。
乳児がずり這い覚えたり、ハイハイやつかまり立ちをするようになりますが、これは基本的には「自然に」覚えていきます。
この自然に覚える学習には失敗がつきものです。
換言すると失敗がないと成功体験につながらない、ということになります。
そういうことからも子どもさんが何か新しいこと(ここではつかまり立ち)をするということは、親が無理やりさせていない限り、失敗を繰り返しながら自然に覚えて言っている行為ということになります。
逆に言うと、「もう立ち上がる時期なのにまだ立たないから」といって、親が無理やり立たせるということは発達的に見て全く意味がないことであるといえます。
そうやって無理に立たせても、それが子どもさんの自発的な学習にはならないので、効果的でないということです。
子どもの関節はすぐには完成しない

子どもの関節が大人のようにできあがるまでには相当な時間がかかります。
乳幼児期はもちろんのこと、小学校の頃でもまだ大人の関節のようにはなっていません(完成していません)。
下肢の関節は立ち上がったり、歩いたり、跳んだり跳ねたりしながら作られていきます。
関節だけでなく、骨も多くの時間をかけて成長していきます。
さて、早くに体重をかけると関節の形成に支障があるのか?ということですが、良くないと言われる根拠になっているのは、大人の膝の変形は体重が増えることで進行する、と思われていることではないでしょうか。
しかし実際はどうかというと、膝の変形が体重の重さだけで決まるものではありません。
O脚やX脚と呼ばれる膝の変形には体重よりも足首(足関節)や足の裏(足底)での体重の支え方が大きく関係します。
その証拠に膝の変形の予防に足底板(靴の底に入れる板)を作ることはよくあることです。
またO脚についても、もともと乳児はO脚であることが多く、これは生理的O脚と呼ばれます。
このO脚は自然に消えていき、成長ととともにやがてX脚になっていきます(このX脚もやがて解消されます)。
平均より少し早く立ったところで、乳児の軽い体重が骨の変形や関節の形成不全に影響を与えることはないといえます。
半年でつかまり立ちをすることと、8ヶ月でつかまり立ちをすることと果たしてどんなに差があるでしょうか。
筋力が弱い時期に立つと関節によくないしO脚の原因になる、という意見も聞きますが、そもそも乳児の筋力は「つかまり立ちや歩きはじめることで強くなって行く」のです。
つまり10ヶ月になったら筋力が知らない間に付いていた、というようなものではありません。
もし半年で立ち上がることが関節に負担がかかるのなら、8ヶ月や10ヶ月で立ち上がるほうが体重が重くなっている分関節によくない、という理屈になってしまいます。
関節の変形や筋力については、大人と同系列で語られていることが問題だと言えるでしょう。
また子どもの、特に乳幼児期の子どもの関節は、とても柔らかくできており、少々関節に無理がかかっても、それでどうにかなってしまうというものでもありません。
例えば大人であれば、頚髄損傷を引き起こすような倒れ方をしても、幼児であれば全く怪我をしないということがあります。
これは乳幼児期の子どもの関節がいかに柔らかくできているかということの証明になります。
これらのことから体重も軽く、繰り返し負担をかけているわけでもない幼児期にそれらのことを心配するのは杞憂でしょう。
それよりもむしろ、つかまり立ちや伝い歩きのときに転倒して頭を打つ、というような事故に気をつけるべきでしょう。
発達は教科書通りにはいかないもの

さて、子どもの発達でもう一つ。
それは教科書通りに発達するとは限らない、ということです。
これはどういうことかというと、子どもによっては教科書的に言われる、ずり這い→四つ這い→立ち上がり→歩行という経過を必ずたどるわけではないということです。
四つ這いをせずにいきなり立ち上がる子やずり這いからなかなか四つ這いに移行しない子どもなど発達は子どもによって違うということです。
また発達の早さも個人によって開きがあります。
親御さんや祖父母の方からすると、その時期を過ぎても自分の子どもがしていないなら漠然と不安になるでしょう。
しかし、順番通りに発達していないからといって、問題があるとは限らないということです。
また運動機能の発達が遅いからといってそれだけで問題とするには根拠が乏しいということになります。
「発達は教科書通りに行かなくて普通」と考えていてよいでしょう。
短期間で成長を判断するのではなく、長期的な視点で子どもさんの成長を見守ってあげてください。
ちなみに私の息子は今つかまり立ちをよくしていますが、ハイハイはあまり上手くなく、高這いは全くと言っていいほどしていません。
かといって体の機能を運動学的に確かめてみても、特に体幹や下肢に問題はありません。
ですから無理やりハイハイをするように仕向けたり、無理やり高這いをするような姿勢を取らせることなく、本人のしたいようにさせています。
いかがでしょうか。
このように子どもの発達には個人差が大きく、「こういう順序でこういう時期にこれこれができないといけない」と思う必要はありません。
はじめにも書きましたが、どうしても心配なら専門家の判断を仰ぐことをお勧めしますが、まずは親御さんが落ち着いて子どもさんの発達をゆったりと見守ってあげましょう。
親の都合で子どもを枠にはめることは、子どもの自発的な発達を逆に壊していることにつながりますので注意が必要です。
最後に。
運動発達が早いからといって運動能力が高いということでもありません。逆に言うと、運動発達が遅くてもスポーツ選手として大成することもあるでしょう。
その辺りは運動発達よりも、幼児期以降の遊び、活動が鍵を握っているといえます。